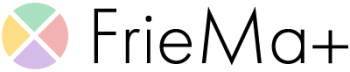「したくないけど、育てたい」
この気持ちは、説明しようとすると途端に矛盾のように見えてしまいます。性行為を前提にしない関係を望みながら、子どもを育てたいと思う。誰かに話すたび、相手の頭の中に「どうやって?」という疑問が浮かぶのがわかります。
でも、その疑問は私の中にもずっとありました。
「したくないけど育てたい」の矛盾を抱く
10代の頃から、子どもと過ごす時間が好きでした。従姉妹の赤ちゃんを抱っこしたとき、ふにゃっとした体温が腕に伝わってきて、胸がじんわりあたたかくなったのを覚えています。
でも、恋愛や性行為に対してはどうしても気持ちが動きませんでした。「親になる」という言葉の向こう側にある“方法”を考えると、体が固まってしまう。
周囲からは「子どもは好きなのに?」と不思議そうに見られます。その視線を受けるたび、「私みたいな人に親になる資格はあるのだろうか」と自分に問いかけてきました。
技術と制度を、現実目線で整理する
子どもを育てたい気持ちと、自分の性への距離感。その2つをどう結びつけるかを考えると、現実的には医療技術や制度の話が欠かせません。
人工授精や体外受精、パートナーとの養子縁組。書類や費用、法律の条件。ネットで調べれば情報は出てくるけれど、その多くは「結婚している男女」を前提に書かれています。
一方で、制度の隙間に生きる私たちは、情報を探すだけでも時間と労力がかかります。「こうすればできる」という道筋があっても、それが自分にとって現実的なのか、経済面や生活環境も含めて何度も計算し直さなければなりません。
子どもを望む気持ちは、勢いだけでは進めないのです。だからこそ、夢と同じくらい、現実を具体的に知っておく必要があります。
情報の壁にぶつかったときの対話先

私は一度、本格的に医療機関に相談しようとしました。電話口で担当者に状況を説明すると、「まずはご結婚されているかどうかをお聞きしてもよろしいですか」と返ってきました。
「いいえ」と答えた瞬間、その先の会話が急にぎこちなくなったのを覚えています。制度やガイドラインが壁のように立ちはだかっている感覚。
そんなときに助けられたのは、同じ立場の人とつながれるオンラインコミュニティでした。そこでは、経験者が具体的な選択肢や実際にかかった費用、行政とのやりとりまで共有してくれます。
情報を得るだけでなく「この気持ちは私だけじゃない」と思える時間が、次の一歩を踏み出すための支えになりました。
家族の定義を更新する勇気

「親になる」という言葉を、もっと広く捉えてもいいのかもしれません。血のつながりや夫婦という枠にとらわれず、子どもを育てる形はひとつではないはずです。
友人同士で育てる選択もあれば、シェアハウスのような形で支え合う方法もある。親と子という2者関係だけでなく、複数の大人が関わる家族も存在します。
私が子どもを望む気持ちは、育てることそのものへの愛情からきています。その気持ちを叶える方法が、一般的なルートと違ってもいい。大切なのは、子どもが安心して暮らせる環境を用意できるかどうかです。
おわりに
「親になる資格」という言葉は、時に自分を追い詰めます。でも、本当は資格というより覚悟と環境の問題なのかもしれません。
あなたがもし同じように「したくないけど育てたい」という気持ちを抱えているなら、その矛盾を否定する必要はありません。方法は一つじゃないし、家族の形も一つじゃない。
大切なのは、自分なりの答えを見つけ、その形を大切にしていく勇気だと思います。