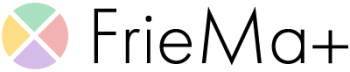結婚して、子どもを持って、家庭を築く——それこそが幸せだと語られる場面に、居心地の悪さや違和感を抱いたことはありませんか?
ニュースでは「子育て世帯」の声に対する政策や地域の取り組みが積極的に取り上げられる一方で、子どもを持たない人生を選んだ人、あるいは持ちたくても持てない事情を抱える人の声が取り上げられることは少ない……
子どもを持つ選択をした人が尊重される雰囲気のある社会のなかで、子どもを持たない選択をした人が抱く違和感や孤立感について掘り下げていきます。
子育て世帯中心的な社会に“私たち”の居場所はない?
少子化が加速している近年は、国や自治体、企業がこぞって「子育て支援」に力を入れています。保育園の拡充、育児休業制度の整備、子育て世帯向けの優遇措置——確かにそれらは、少子化や労働力不足という日本の課題への対策として必要かもしれません。
しかし、このような社会の動きのなかで、子どもを持たない人たちが感じるのは「取り残されている」という感覚。
税制や手当の優遇から、地域のイベントや施設の利用にいたるまで、社会の重心が子育てをしている人に偏っているような気がする——自分の選択や生活スタイルが尊重されないと悩むことも少なくないはずです。
子どもを持たないという選択をした私たちの声にも耳を傾けてほしい、けれど「子どもは未来の宝なんだから」と言われると主張しづらい、そんな空気が生まれます。
ただ、誰かの当たり前が誰かを静かに傷つけている可能性があることを、私たちは忘れてはいけないと思うのです。
“普通”の幸せからはみ出す恐怖と孤独
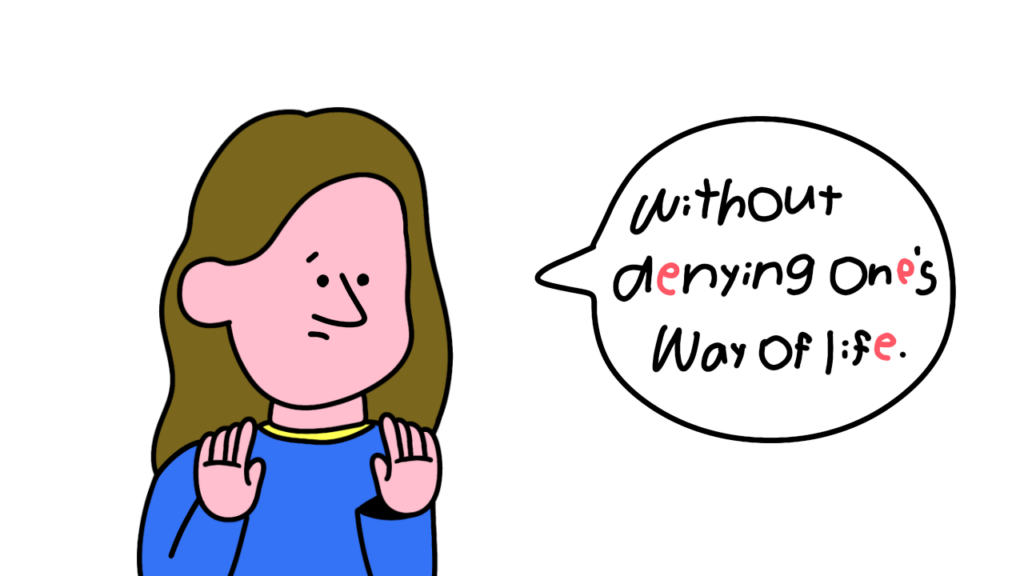
何気ない会話のなかで、「いつ結婚するの?」「子どもはまだ?」と尋ねられた経験はありませんか?本人にとってはただの雑談——しかし、聞かれる側にとっては、自分の生き方を否定されたような気持ちになることもあります。
こうした無自覚な言葉が与えるプレッシャーは計り知れない。なぜなら、結婚や出産が「当たり前」とされる社会では、その道から外れる選択をする人は「何か足りない存在」とみなされがちだからです。そうやって、誰かのなかに孤独感や劣等感が生まれる。
本来は誰もがそれぞれの生き方を大切にしていいはずなのに、世間の“普通”から外れたとたんに、肩身の狭さを感じさせられることがあります。気づけば、自分は社会の外にいるような感覚にとらわれてしまうのです。
なぜ「子どもがいない人」の声は届きにくいのか
子育て世帯への支援が手厚くなる一方で、「子どもがいない人」に関する施策や発信は圧倒的に少ないのが現状。単身世帯の生活支援、高齢期に向けた備え、孤立防止といった観点は、ようやく語られ始めたばかりです。
では、なぜ子どもがいない私たちの声は届きにくいのでしょうか。その背景には「支援=困っている人を助ける」という構図があると思うのです。
社会が「子育て世帯=支援が必要な人たち」と捉え、手厚く支援する。そうすると、それ以外の人たち、たとえば子どもを持たない人や単身者、高齢の一人暮らしの人などの生活上の困りごとには目が向きにくくなる。こんな流れが生まれているような気がします。
でも本来、社会とは多様な人々が対等に共存する場所。子育てしている人もしていない人も、高齢者も若者も、どんな属性であっても尊重されるべき存在です。その視点が欠けたとき、「多様性」や「共生」という言葉もきれいごとになってしまうのではないでしょうか。
子どもがいない人生にある豊かさと意義
社会の価値観が子育て世帯に傾いていると、「子どもを持たない人生は間違いなのかもしれない」と感じてしまうことがあるでしょう。でも、どの人生が正解で間違いかなんてなくて、自分で選択した人生が幸せだと感じるのなら、それでいいのです。
私たちは、親にならなくても人を支え、社会に貢献することができるはずです。教育や福祉の現場、地域活動、職場のなかで子どもを持たない立場だからこそ担える「中立的な役割」も存在するのではないでしょうか。
そしてなにより、私たち一人ひとりの生き方そのものが、同じ立場にある人へのメッセージとなり希望となります。「こういう人生もあっていい」「こんな選択もあっていい」と示すことは、誰かの選択肢を広げるかもしれません。
あなたの選択には確かな価値がある
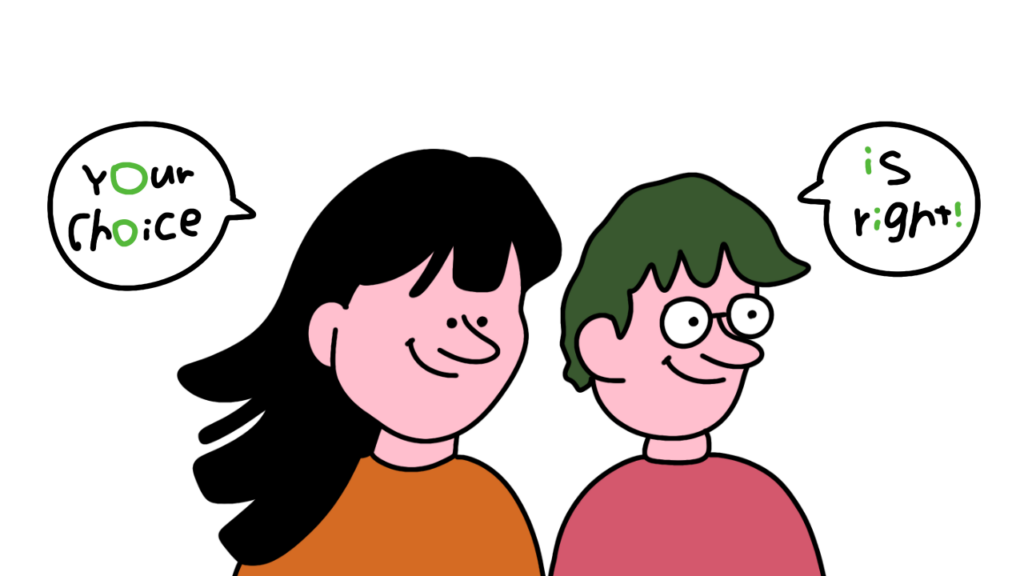
子育て世帯への支援が手厚い社会で、子どものいない人生を選択した人は「声が届かない」と感じることがあるかもしれません。
日々のなかで、孤独を感じたり自分の選択が間違いかもしれないと悩んだり——けれど、あなたの選択は決して間違いではなく、抱いている違和感や思いには、確かな価値があります。
近年、社会は少しずつ変化しています。家族のカタチやライフスタイルは多様化していて、子どもを持たない人生への理解も深まっていくはずです。
だからこそ、私たちは声が届いていないように感じても、自分の選択に誇りと自信を持って生きていく——それこそが誰かにとっての安心感や選択肢の広がりにつながって、いずれ社会を変化させる力になる。
子育てをする人だけでなく、しない人、できない人——あらゆる人が尊重される社会につながる一歩は、私たち自身が自分の選択や価値を疑わないことかもしれません。