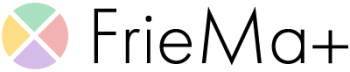画面の向こうには、小さなリビングが広がっていた。
それは誰かの家でも、どこかのカフェでもない。Zoomの四角い枠のなか、6人ほどが穏やかに笑い合っていた。誰かが話し、誰かがうなずき、誰かが「それ、わかります」とチャットを打つ。孤独を抱えた人たちが、同じ時間に集い、心の温度を少し上げていく――それが、フレマのオンライン会だ。
「フレマ」は、友情結婚や性的マイノリティのパートナー探しを支援するマッチングアプリ。
アプリ上でメッセージをやり取りするだけでは伝わりにくい価値観や、他人には話しづらい本音を共有できる場として、毎月リアルイベントを開催している。2025年8月、その試みはついにオンラインへと広がった。全国各地から、6〜7名の参加者がZoom上に集まり、“恋愛や結婚だけがすべてじゃない生き方”について語り合った。
「恋愛感情がわからない」と言葉にする勇気

話が展開していくきっかけは、ふっと発される、さまざまな言葉だ。
「恋愛感情って、みなさんどう感じますか?」
「恋愛をしたくないわけじゃない。でも、日によって“女の気分じゃない”ことがある」
「グレーセクシャルという言葉が、一番しっくりくるかもしれない」
恋愛や性欲に波がある――その感覚を“おかしい”と思わずに話せる場所は、現実では驚くほど少ない。ある人は「恋愛感情がわからない」と打ち明けたとき、相手に「そんなのかわいそう」と言われたという。「恋をしない=人間らしくない」とでも言いたげな反応に、ただ苦笑するしかなかった。
オンライン会では、そんな経験を共有できる。
誰かの言葉にほかの誰かが頷き、チャット欄に「それ、まさに私も同じ」とコメントが流れる。その共感の連鎖が、孤立感を少しずつ溶かしていく。恋愛感情も、性的欲求も、まるで天気のように移ろうもの。そんな当たり前のことを、あらためて確認できる時間だった。
「子どもを持たない人生」は本当に寂しい?
「子どもを持つ・持たない」問題も根強い。
「精子バンクに興味がある」「パートナーはいらないけど、子どもはほしい」――そんな率直な声が挙がる一方で、「子どもがほしいと思ったことがない」「いまはいいけれど、50代になったら後悔するかもしれない」と語る人もいる。
なかには「里親制度の説明会に行ったけど、単身女性にはハードルが高かった」と打ち明ける方もいた。育児経験がないと難しい、という現実に直面してしまうと、そもそも母親になる以前に、自分はひとりの人間としてどう生きたいんだろう、と自問するきっかけにもなりそうだ。
社会は“母になること”に過剰な理想を押し付ける。
「女性の人生=子どもを育てること」という価値観が根強く残るなかで、「育てたい」ではなく「育める関係を築きたい」と語る人たちが、確かにいるのだ。
Zoomの擬似リビングが作りだす“地続きの非日常”

多くの参加者が口を揃えるのは、「リアルでは自分のセクシャリティや恋愛観を話せる場所がない」ということ。
会社でも家庭でも、“普通”を演じ続ける日常のなかで、Zoomの画面が“地続きの非日常”をつくり出している。画面の向こうの人たちが頷きながら話を聞いてくれるだけで、自分の存在が認められるような感覚が生まれるのだ。
“擬似リビング”とは、他者の生活の一部がほんの少し垣間見える空間。カメラ越しに見える本棚や壁のポスターが、会話のきっかけになることもある。オンライン会がもたらすのは、物理的距離を超えた“心理的距離の近さ”だ。
孤独の対策とは、他者に依存することではなく、“安心して本音を話せる場所”を持つこと。Zoomのオンライン会は、参加者にとってまさにそのセーフスペースとして機能している。
思考や創造の源になる“孤独”
オンライン会では、誰かの発言が、別の誰かの気づきへと変わっていく。「恋愛感情がわからない」「一人でいる時間が好き」という言葉をきっかけに、それぞれが自分の価値観を再確認する。正解を求める人はいないからこそ、孤独が思考や創造の源になるのだ。
Zoomの画面上で交わされる会話は、まるで“つながりのリハビリ”のようだ。最初は緊張していた人も、時間が経つにつれ、少しずつ表情が柔らかくなる。孤独を否定せず、他者とのあいだに小さな橋をかけていく――その積み重ねが、オンライン会の最大の効用なのかもしれない。
リアルでは出会えなかった人たちが、画面越しに顔を合わせ、それぞれの“いま”を話す。その光景は、現代の新しい共同生活のようにも見える。恋愛や結婚を前提としない関係性を模索する人々にとって、オンライン会は「共感のリビングルーム」だ。
孤独はなくならない。けれど、孤独を抱えたまま話せる場所があれば、人は驚くほど前向きになれる。Zoomという画面の向こうに広がる小さな灯りが、誰かの夜を照らしているのかもしれない。