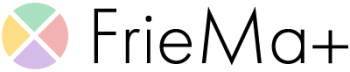就活に悩む大学生・速水翔太(城桧吏)が、68歳の女性3人が暮らすシェアハウスで雑用係として働き始めるドラマ『終活シェアハウス』。そこには、人生経験が豊富な彼女たちの知恵・料理・生活の工夫、そして生き方の哲学が込められていた。
一方で、ただ「楽しい老後」では終わらない。軽度認知障害の恒子(市毛良枝)が新たに加わったことで、健康・仕事・老い・経済・恋愛など、さまざまな“現実”が一気に濃度を増していく。そこで描かれるのは、諦めや閉塞ではない。「人生の終盤」を“終わり”ではなく、“いまある時間の使い方の最適化”として扱っている。
いま、ここに生きている自分を否定せずに、背伸びもしないままで、“いま”をどう丁寧に扱うか。ここが、このドラマの芯である。
終活を描きながら「いまをどう生きるか」へ視点を引き戻す

恋人や家族という単位に括られなくても、人は“誰かとゆるくつながりながら”生きていけるはず。恋愛感情は絶対的なものではなくて、無理して家族をつくろうとしなくても、このドラマの奥村歌子(竹下景子)、今井厚子(室井滋)、池上瑞恵(戸田恵子)たちのように、友情を継続させながら暮らしを成立させることだって、できるんじゃないだろうか。
このドラマ『終活シェアハウス』は、そんな希望に真っ直ぐ光を当ててくれる。
たまたま彼女たちと交流するようになった青年・翔太は、カメハウスの女性たちの人生を救おうとしているわけではない。そして女性たちも、翔太の将来を上から目線で勝手に決めようとはしない。
それぞれの足元にある“小さな現実”を共有しながら、ただ一緒にご飯を食べたり、笑ったり、必要なときだけ手を貸しあったりする。恋愛感情から始まって終わる関係性ではなくて、名前付けや役割で縛ることもない。その様が、とても豊かに映る。
孤独は“持ってはいけないもの”じゃない。孤独はときに、静かでやわらかい余白として存在していい。このドラマはそこに、まるでそよ風のように寄り添ってくれる。
若い世代とシニア世代がアップデートし合う「ジェネレーション・インスパイア」

翔太は人生の先輩たちから「効率のいい解決法」ではなく、“生き方の手ざわり”を受け取っていく。反対に、彼女たちは翔太やその友人の林美果(畑芽育)から、“まだ試していい未来が残っている”という事実を思い出していく。
教える側・教わる側といった、上下の構図ではない。彼らは些細なやりとりから相互に刺激し合い、お互いの価値観を少しずつアップデートし続けているのだ。それが、恋愛的役割でも血縁でもない関係のなかで生まれ得るのだということが、このドラマを通じて知れる。
高齢者が直面する問題は、本来ものすごく重いもの。認知、仕事、恋愛、経済……。それでも、誰かひとりの肩に背負わせず、ちいさな分担で乗り越えていくとき、“生き抜くこと”の意味がもっとやわらかくなるのかもしれない。
終活とは「静かに幕を閉じる儀式」ではない。終活とは、「自分の最終章を、最適に使い切るための編集作業」だ。
カメハウスの日常は、しんどさのすぐとなりに、笑いとお茶の湯気が同居している。料理の得意な歌子が、渾身の腕前でアクアパッツァを振る舞ったり、タルトタタンをお茶菓子にして話に花を咲かせたり。
人生は、案外、このくらいの密度でちょうどいいのかもしれない。
固定化された関係性の外側に「救い」はちゃんとある
ドラマ『終活シェアハウス』は、家族でも恋人でも職場仲間でもない関係が、人生を救い得ることを見せてくれる。
特定のパートナーがいなくてもいい。名前で規定される関係じゃなくてもいい。与えられた役割を果たすのに躍起になって、歯を食いしばりながら、自分の存在価値を証明しなくてもいい。
ただそこに“いる”こと。ただ“つながっている”こと。ただ“同じ場所で生きている”こと。そんなゆるいつながりが、人生をふっと軽くする。
孤独は寂しいだけじゃない。孤独は、選べる自由のひとつでもあるのだから。